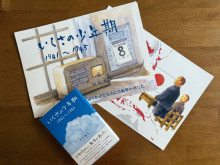(一社)福井環境研究開発は7月26日(土)、「ざわザワ高校 ~海の未来をつなぐ哲学~」の第2回授業を開催しました。2回目の授業には、福井県内在住の高校生12人とジャーナリストの堀潤さん、哲学者の岩内章太郎さんに参加いただきました。この海洋教育プログラムは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で行っています。

イベント概要
・開催概要:「ざわザワ高校 ~海の未来を変える哲学~」第2回授業・日程:2025年7月26日(土)
・開催場所:人道の港敦賀ムゼウム・敦賀市役所(敦賀市)
・参加者:ジャーナリスト・堀潤さん、哲学講師・岩内章太郎さん、高校生12人、地域ゲスト1人
・番組:「ざわザワ高校 ~海の未来を変える哲学~#3,4」
〇放送 福井テレビ 1.9/27(土) 2.10/25(土) 各10:55~11:25 ※予定
〇配信 YouTube 福井テレビチャンネル www.youtube.com/@fukuitv8ch
TVer https://tver.jp/
敦賀ならではの“哲学対話”を… 第1部のテーマは「幸せの本質とは?」
「ざわザワ高校」の最大の特徴は、答えのない問いについて、多様な立場の人がフラットに対話し、物事の本質を探る「哲学対話」にあります。今回は哲学対話をする前に敦賀市にある資料館「人道の港敦賀ムゼウム」を訪れ、敦賀に伝わる2つの人道の歴史について学びました。ガイドを務めたのはざわ高生の4人、「みらい、りんな、ハラ、タッキー」です。4人は地元の敦賀高校に通い、これまでこの資料館に訪れた人にガイドをするボランティアにも取り組んできました。今回はその経験を生かし、堀さんや他の生徒たちに「ポーランド孤児」と「ユダヤ難民」という敦賀が過去に2度海外難民を受け入れた歴史を紹介しました。
資料館の見学が終わると哲学者の岩内先生は「敦賀には海をわたって2回も難民が逃げ延びた歴史がある。今回学んだことを生かして、”幸せ”をテーマに哲学対話をしましょう」と発表しました。
生徒たちは場所を敦賀市役所に移し、哲学対話を開始。ファシリテーターの堀潤さんが巧みに会話を促し、岩内先生が対話を深める問いを投げかけることで、生徒たちは安心して本音を話せる心理的安全性を確保。生徒たちは敦賀ムゼウムで学んだことや実体験に基づく「幸せ」についておよそ80分間対話を重ねました。最終的に導き出された幸せの本質は「欲求や欲望が満たされた時に感じる状態、自分だけのものと他者と共有できるものがある」というものでした。そして、堀さんは「日本は海に囲まれていたことで1920年~40年代にかけて混乱するヨーロッパと関わりを持たずに済んだ。海がバッファーゾーン=緩衝地帯の役割を果たしたことになり、難民を含め人々を包摂する装置にもなっていた」と結論付けました。

第2部は地域ゲストも参加! 「敦賀フグ」の養殖から見えてくるつながりとは
第2部では、ゲストに敦賀市で敦賀フグの養殖をする漁師の石川恵さんを招いて哲学対話を行いました。授業の前半では事前にざわ高生の二人(ウギとRNA)が石川さんの仕事に密着取材した様子をVTRにまとめて紹介。生徒たちは「敦賀フグが消費者の食卓に届くまでには”稚魚屋さん”や”エサ屋さん”、”漁連”や”組合”といった様々な関係者が関わっていて、漁師だけで成り立つものではない」ということを学びました。VTRを見終わると料理人の顔も持つ石川さんが調理した「敦賀フグのたたき」が生徒たちにふるまわれました。
第2部でも哲学対話を実践! テーマは「つながり」
ゲストの石川さんは漁師でありながら料理人として育てた魚を消費者に直接販売もしています。そのため多くの人から手数料がかからない直販の拡大を進められるそうですが、石川さんは「漁師は人とのつながりで成り立つ職業。直販を拡大するつもりはない」と生徒たちに人とのつながりを大切にしてほしいと訴えました。そこで、第2部では「つながり」をテーマに哲学対話をすることになりました。今回はMC(学級委員長)の堀さんも生徒側の席に座り、生徒と同じ目線で哲学対話を行いました。堀さんは「”つながり”と聞くと分断が思いつく。あの人とはつながりたいが、あの人とはつながりたくない、という世の中になっている」と問題提起をしました。それに対して生徒は「つながりたくない人とはつながらなくていいと思う」や「つながりたい人とだけつながると思考が極端になる」またある生徒は「”幸せの哲学対話”とも関係するが、つながりは海を越えるために生まれた技術」「人は一人では生きていけない、つながることは生きていくため」といった様々な意見が出ました。最終的に哲学講師の岩内先生は「つながりはポジティブな面とネガティブな面があるが、大事なのはつながりを拒む人達に対してどのようにアプローチをするかを考える事ではないか」としました。

「海の可能性」を探る旅は始まったばかり
「ざわザワ高校」が目指すのは、課題解決ではなく、海や沿岸地域の「新しい可能性」の発見。今回の授業は、まず自分を知り、他者を知り、地域を知ることから、その探求が始まることを示してくれました。生徒たちが自ら問いを立て、多様な人々と対話しながら本質を探っていくこのプロセスは、互いの違いを認め合い、新しい価値を共に創造していくための貴重な経験となるでしょう。これから一年間、彼らがどのような「海の可能性」を見つけ出し、社会に発信していくのか。今後の活動から目が離せません。

<団体概要>
団体名称:一般社団法人福井環境研究開発
URL:https://fukui.uminohi.jp/
活動内容:北は東尋坊にみる奇岩断崖が続く越前海岸、南は優美なリアス式海岸の若狭湾と変化に富んだ福井県の海は、北前船などの海上交通の要衝として古くから栄えてきました。また、寒流と暖流が交わる福井県沖は越前がにや若狭ガレイなど海産物の宝庫。(一社)福井環境研究開発では、海に親しみ、大切にする心を育む運動を進めています。

日本財団「海と日本プロジェクト」
さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。
https://uminohi.jp/